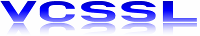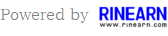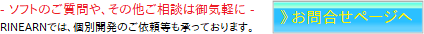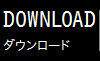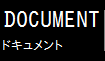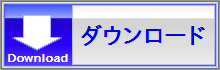» 詳しい使用方法や、エラーで展開できない際の対応方法などはこちら
円周率1万桁の計算(ガウス=ルジャンドル法)
このプログラムは、 ガウス=ルジャンドル法 を用いて、円周率を1万桁まで計算するVCSSLプログラムです。
使用方法
ダウンロードと展開(解凍)
まず、PC(スマホは未対応)で上の画面の「 ダウンロード 」ボタンを押してください。 するとZIP形式で圧縮されたファイルがダウンロードされます。
その後、ZIPファイルを右クリックして「すべて展開」や「ここに展開」などで展開(解凍)してください。 展開が成功すると、ZIPファイルと同じ名前のフォルダができ、その中にZIPファイルの中身が入っています。
» 展開がエラーで止まってしまう場合や、ファイル名が文字化けしてしまう場合は…
プログラムの起動
Windows をご使用の場合
上記でZIPファイルを展開したフォルダ内にある、以下のバッチファイルをダブルクリック実行してください:
もしプログラムを書き変えながら使いたい場合は、代わりに「 VCSSL_Editor__プログラム編集はこちら.bat 」を実行してください。
正常に起動できると、初回のみ、Java実行環境を入手するか等を尋ねられるので、適時答えて済ませると、プログラムが起動します。 2回目以降はすぐに起動します。
Linux 等をご使用の場合
ZIPファイルを展開したフォルダ内へコマンドライン端末で cd して、以下の通り入力して実行してください:
(プログラムの内容を書き変えながら使いたい場合は、代わりに VCSSL_Editor.jar を実行)
» javaコマンドが使用できない等のエラーが表示される場合は…
操作方法
プログラムを実行すると、負荷に関する注意メッセージが表示され、実際に円周率を計算するかどうかを尋ねられます。そこで「はい」を選択すると、円周率の計算がスタートします。
計算時間は、最近のパソコンであれば概ね10秒を切りますが、古いパソコンや、低性能の省電力パソコンなどでは、より長い時間を要します。 計算途中で強制終了したい場合はウィンドウを閉じてください。
計算が完了すると、画面に円周率1万桁と、計算に要した時間が表示されます。
最後に、計算結果をファイルに保存するか尋ねられます。「はい」を選択した場合は「pi.txt」に結果が保存されます。
題材解説
ガウス=ルジャンドル法
ガウス=ルジャンドル法 は、円周率を計算するための強力なアルゴリズムです。 同じ変数に対して計算を繰り返す事によって、真の値に収束させていくタイプのアルゴリズムで、特筆すべきはその収束の速さです。 具体的には、ループを一周するごとに、値の精度(正しい桁数)が毎回倍増していくという、驚異的な収束特性を誇ります。 つまり、ループ回数に対して、精度が指数関数的に向上します。
円周率を求めるアルゴリズムとしては、他にも arctan 関数や arcsin 関数のマクローリン展開(0近傍でのテイラー展開) を用いたものが有名です。 しかしガウス=ルジャンドル法は、それらに比べて遥かに高速である上に、アルゴリズムの複雑さも大差ありません。
ガウス=ルジャンドル法による円周率計算の処理
ガウス=ルジャンドル法では、以下の漸化式を繰り返し処理する事によって、円周率計算に必要な値の組を収束させ、最後にそれらの値から円周率を求めます。
\[ a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \ \ … (1) \]
\[ b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} \ \ … (2) \]
\[ c_{n+1} = c_n - d_n(a_n-a_{n+1})^2 \ \ … (3) \]
\[ d_{n+1} = 2 d_n \ \ … (4) \]
なお、各変数の初期値は以下のように指定します。
\[ a_{0} = 1 \ \ … (5) \]
\[ b_{0} = \frac{1}{\sqrt{2}} \ \ … (6) \]
\[ c_{0} = \frac{1}{4} \ \ … (7) \]
\[ d_{0} = 1 \ \ … (8) \]
これらの\( a_n \) 〜 \( d_n \)の(\(a_nとb_nが収束した時点における\))収束値の組を用いて、円周率\( \pi \)の近似値は以下のように求まります。
\[ \pi = \frac{ ( a_n + b_n )^2 }{ 4 c } \ \ … (9) \]
こうして得られる\( \pi \)における信頼できる桁数は、\( 2^n \) のオーダーで極めて俊敏に向上します。
ニュートン法による平方根計算の処理
さて、上で述べたガウス=ルジャンドル法の処理は極めて単純ですが、一つ飛ばしている点があります。それは(2)式と(6)式で平方根を使用している事についてです。 つまり、ガウス=ルジャンドル法によって円周率を計算するためには、まず平方根を計算する処理を用意する必要があります。
このプログラムでは、平方根の計算にはニュートン法を採用しています。 ニュートン法もまた、繰り返し計算によって値を収束させていくタイプのアルゴリズムです。ここではニュートン法そのものについて詳しく述べる事はせず、平方根を求める処理だけを簡潔に解説します。
まず、変数\(x\)が、与えられた\(a\) の平方根 \(\sqrt{a}\) の値に等しい時に \( f(x) = 0 \) となるような、関数\( f(x) \)を定義します。具体的な定義は以下のようになります。
\[ f(x) = x^2 - a \]
この\( f(x) \)は、確かに\( x = √a \)の時に\( 0 \)となります。この\( f(x) \)を基にして、以下のような漸化式を作ります。
\[ x_{n+1} = x_{n} - \frac{f(x)}{f'(x)} \]
これがニュートン法の一般的な漸化式で、\( x_{n} \)の収束値として\(f(x_{n}) = 0\)を満たす値が得られます(収束するためにいくつかの条件はありますが)。ここに上で定義した\( f(x) \)を具体的に代入して:
\[ x_{n+1} = x_{n} - \frac{ x_{n}^2 - a }{ 2 x_{n} } \]
このままでも良いのですが、少しでも計算回数を節約したいので、もう少しまとめると:
\[ x_{n+1} = \frac{1}{2} \{ x_n + \frac{a}{x_n} \} \ \ … (10) \]
という漸化式が得られます。
(10)の漸化式は、繰り返し処理する度に、\(x_{n+1}\)の値が\(\sqrt{a}\)の値に近づいて行きます。つまり適当な \( x_0 \) からスタートして、\(x_{n+1}\)と\(x_n\)の値がほぼ同じ値に収束するまで回すと、\( x_n \)に\( \sqrt{a} \)の値が得られます。
コード解説
ここからは、実際に円周率を求めるコード内容について解説します。
まずは、コード全体をそのまま掲載します。
coding UTF-8;
import Time;
import Text;
// 円周率を求める桁数
const int DIGIT = 10000;
// 結果を記載するファイル
const string FILE_PATH = "pi.txt";
// 計算進行状況を表示するかどうか
const bool PRINT_PROGRESS = true;
/*
* main関数:
* プログラムの実行開始時に、まずこの関数が呼び出される
*/
void main(){
// varfloat型(多倍長浮動小数点型)の演算桁数を設定する
digit( DIGIT * 1.1 ); // 1割くらいマージンを設ける
if( DIGIT <= 100 ){
digit( DIGIT + 10 ); // 100桁以下の時は念のため+10桁
}
if( PRINT_PROGRESS ){
println( "計算中…" );
println( "------------------------------" );
}
// 計算開始時刻を記録
int start = time();
// !!!!!
// ここで円周率を計算
// !!!!!
varfloat piValue = pi( PRINT_PROGRESS );
// 結果を見やすい形で出力
string text = getOutputText( piValue, DIGIT );
println( "------------------------------" );
println( text );
// 計算所要時間(ベンチマークスコア)を表示
if( PRINT_PROGRESS ){
// 計算所要時間を求めて表示
float totaltime = millisecond( time() - start ) / 1000.0;
println( "------------------------------" );
println( "計算完了" + EOL );
println( "SCORE " + totaltime + " SEC" );
}
// 結果をファイルに出力
bool save = confirm( "結果をファイルに保存しますか ?" );
if( save ){
save( FILE_PATH ); // CONSOLEの内容をファイルに出力
alert( FILE_PATH + " に保存しました。" );
}
}
/*
* 平方根 √a を計算する関数(ニュートン法)
* 収束を速くするため、開始値として近い値をstartに与える
*
* ※varfloat型は、多倍長精度の浮動小数点を扱う型
*/
varfloat sqrt( varfloat a, varfloat start ){
varfloat value = start;
varfloat valueStock = -1.0vf;
while( value != valueStock ){
valueStock = value;
value = ( value + a / value ) * 0.5vf;
}
return value;
}
/*
* 円周率を計算する関数(ガウス=ルジャンドル法)
* 引数 printProgress は、trueなら計算進行状況を表示する
*
* ※varfloat型は、多倍長精度の浮動小数点を扱う型
*/
varfloat pi( bool printProgress ){
int start = time(); // 処理開始時間
// アルゴリズムで使う変数
varfloat value = 0.0vf;
varfloat a = 1.0vf;
varfloat b;
varfloat aStock = 0.0vf;
varfloat bStock = 0.0vf;
varfloat c = 0.25vf;
varfloat d = 1.0vf;
// bの初期値を1/√2 = √0.5に設定
// 2個目の引数の即値は、収束初期値で、結果に近い値
b = sqrt( 0.5vf, 0.7071067811865475vf );
// ガウス=ルジャンドル法による
// 円周率の収束アルゴリズム
int loopCount = 0;
while( a != aStock && b != bStock ){
aStock = a;
bStock = b;
a = ( aStock + bStock )*0.5vf;
// 平方根の計算、収束高速化のため前ループの結果からスタート
b = sqrt( aStock*bStock, b );
c = c - d*( a - aStock )*( a - aStock );
d = 2.0vf*d;
// 計算進行状況を表示
if( printProgress ){
// 現在までの計算所要時間
float sec = millisecond( time() - start ) / 1000.0;
loopCount++;
println( loopCount + " ループ完了 / " + sec + " SEC" );
}
}
value = (a+b)*(a+b) / (4.0vf*c);
return value;
}
/*
* 長い桁数(digit)の円周率を、読みやすい文字列に整形する関数
*/
string getOutputText( varfloat piValue, int digit ){
int lineColumnN = 10; // 行あたり列数
int columnWidth = 10; // 1列あたり文字数
int currentIndex = 0; // 現在の文字位置を控える
int blockLineN = 10; //1ブロックごとの行数
int lineN = digit / (lineColumnN*columnWidth); //総行数(自動計算)
string outputText = "3." + EOL; // 結果の出力用文字列
string piText = (string)piValue; // 円周率の文字列
// 先頭の "3." を除外
piText = substring( piText, 2, (lengthOf(piText)-1) );
for( int i=0; i<lineN; i++ ){
// 一行の内容を書き出す
for( int j=0; j<lineColumnN; j++ ){
// 切り取り始点インデックスを求める
int subindex = i*lineColumnN*columnWidth + j*columnWidth;
// 始点インデックスから、1列あたり文字数の分だけpiTextを切り取り、outputTextに追加
outputText += substring( piText, subindex, subindex+columnWidth );
outputText += " ";
}
// 行の折り返し
outputText += EOL;
// ブロックの区切り行ごとに、現在の行数を表示する
if( (i+1)%blockLineN==0 ){
outputText += EOL + " - " + (i+1)*lineColumnN*columnWidth + " DIGIT -" + EOL + EOL;
}
}
return outputText;
}
以上の通りです。それでは、細部を見ていきましょう。
ライブラリの読み込み
まずは、プログラムの先頭領域で、必要なライブラリを読み込んでいます。
円周率を計算する肝心な部分に関しては、ゼロから組んでいるため、特別なライブラリは必要ありません。 しかし、計算時間を計測したり、結果を読みやすい形に加工して表示したりするために、標準ライブラリである「 Time 」ライブラリと「 Text 」ライブラリを import で読み込んでいます:
coding UTF-8;
import Time;
import Text;
なお、先頭行の「 coding UTF-8; 」の行は、コードを記述している文字コードを宣言しているもので、必須ではないですが、書いておくとメッセージの文字化け等を防げます。
main 関数: 外枠の処理フロー
続いて、いくつかのパラメータ/フラグを定義した後、main 関数を定義しています。
この main 関数は、C系言語ユーザーの方ならおなじみですね。プログラムの実行開始時に、最初に呼び出される関数で、処理フローの外枠が実装されています。
// 円周率を求める桁数
const int DIGIT = 10000;
// 結果を記載するファイル
const string FILE_PATH = "pi.txt";
// 計算進行状況を表示するかどうか
const bool PRINT_PROGRESS = true;
/*
* main関数:
* プログラムの実行開始時に、まずこの関数が呼び出される
*/
void main(){
// varfloat型(多倍長浮動小数点型)の演算桁数を設定する
digit( DIGIT * 1.1 ); // 1割くらいマージンを設ける
if( DIGIT <= 100 ){
digit( DIGIT + 10 ); // 100桁以下の時は念のため+10桁
}
if( PRINT_PROGRESS ){
println( "計算中…" );
println( "------------------------------" );
}
// 計算開始時刻を記録
int start = time();
// !!!!!
// ここで円周率を計算
// !!!!!
varfloat piValue = pi( PRINT_PROGRESS );
// 結果を見やすい形で出力
string text = getOutputText( piValue, DIGIT );
println( "------------------------------" );
println( text );
// 計算所要時間(ベンチマークスコア)を表示
if( PRINT_PROGRESS ){
// 計算所要時間を求めて表示
float totaltime = millisecond( time() - start ) / 1000.0;
println( "------------------------------" );
println( "計算完了" + EOL );
println( "SCORE " + totaltime + " SEC" );
}
// 結果をファイルに出力
bool save = confirm( "結果をファイルに保存しますか ?" );
if( save ){
save( FILE_PATH ); // CONSOLEの内容をファイルに出力
alert( FILE_PATH + " に保存しました。" );
}
}
上の通り、処理内容は
- まず桁数を設定
- 続いて円周率計算を行う pi 関数(すぐ後で中身を掲載) を呼ぶ
- 最後に結果を整形して表示
という流れになっています。
ニュートン法による平方根計算の実装(sqrt 関数)
その後は、後のガウス=ルジャンドル法の実装での円周率計算に必要になる、平方根を求める処理が sqrt 関数に実装されています。
具体的には、(10)式をほぼそのまま、収束するまで繰り返しています。 収束の判定には、一回前のループ時点での値を変数 valueStock に保持しておき、1回処理後に値が変わっていなければ、収束したとみなす方法を用いています(末尾桁が振動するようなケースでは、ある程度絶対値が接近した時点で収束と見なす必要がありますが、今回の場合は必要ありません)。
/*
* 平方根 √a を計算する関数(ニュートン法)
* 収束を速くするため、開始値として近い値をstartに与える
*
* ※varfloat型は、多倍長精度の浮動小数点を扱う型
*/
varfloat sqrt( varfloat a, varfloat start ){
varfloat value = start;
varfloat valueStock = -1.0vf;
while( value != valueStock ){
valueStock = value;
value = ( value + a / value ) * 0.5vf;
}
return value;
}
なお、2個目の引数 start には、ニュートン法の初期値を指定するようにしています。ニュートン法では、初期値が収束値に近いほど、高速な動作が期待できます。
今回は、ガウス=ルジャンドル法の収束部で平方根を求めるので、非常に近い平方根の値を、収束ループ毎に何度も求める事になります。そこで、ガウス=ルジャンドル法の前回ループ時の結果を保持しておき、次回ループ時の初期値に与える事で、平方根の収束を速めています。
ガウス=ルジャンドル法による円周率計算の実装( pi 関数)
さて、次はいよいよ、ガウス=ルジャンドル法で円周率を求める部分の実装です。これは pi 関数として実装されています。
これは素直に、初期値を設定して、(1)〜(4)式を繰り返し処理しています。平方根と同様、変数 a と b の値を、変数 aStock と bStock に保持しておき、収束ループを一周しても値が変わっていなければ、収束したと見なしています(これも場合によっては、絶対値がある程度接近した時点で収束と見なす必要がありますが、今回は必要ありません)。
/*
* 円周率を計算する関数(ガウス=ルジャンドル法)
* 引数 printProgress は、trueなら計算進行状況を表示する
*
* ※varfloat型は、多倍長精度の浮動小数点を扱う型
*/
varfloat pi( bool printProgress ){
int start = time(); // 処理開始時間
// アルゴリズムで使う変数
varfloat value = 0.0vf;
varfloat a = 1.0vf;
varfloat b;
varfloat aStock = 0.0vf;
varfloat bStock = 0.0vf;
varfloat c = 0.25vf;
varfloat d = 1.0vf;
// bの初期値を1/√2 = √0.5に設定
// 2個目の引数の即値は、収束初期値で、結果に近い値
b = sqrt( 0.5vf, 0.7071067811865475vf );
// ガウス=ルジャンドル法による
// 円周率の収束アルゴリズム
int loopCount = 0;
while( a != aStock && b != bStock ){
aStock = a;
bStock = b;
a = ( aStock + bStock )*0.5vf;
// 平方根の計算、収束高速化のため前ループの結果からスタート
b = sqrt( aStock*bStock, b );
c = c - d*( a - aStock )*( a - aStock );
d = 2.0vf*d;
// 計算進行状況を表示
if( printProgress ){
// 現在までの計算所要時間
float sec = millisecond( time() - start ) / 1000.0;
loopCount++;
println( loopCount + " ループ完了 / " + sec + " SEC" );
}
}
value = (a+b)*(a+b) / (4.0vf*c);
return value;
}
引数 printProgress には、計算の進行状況を表示するかどうかを指定できるようにしています。true の場合は、収束ループが一周するごとにタイムを表示します。
その他、表示内容の整形など
それ以外にも、表示内容を見やすい形のテキストに整形する処理などが実装されています。 が、本質とはあまり関係ない雑多な処理であるため、ここでは割愛します。
ライセンス
このVCSSL/Vnanoコード( 拡張子が「.vcssl」や「.vnano」のファイル )は実質的な著作権フリー(パブリックドメイン) である CC0 の状態で公開しています※。 記事中にC言語/C++/Java言語などでのサンプルコードが掲載されいてる場合は、それらについても同様です。 そのままでのご利用はもちろん、改造や流用などもご自由に行ってください。
※ ただし、このコードの配布フォルダ内には、ダウンロード後すぐに実行できるように、 VCSSLの実行環境も同梱されており、そのライセンス文書は「 License 」フォルダ内に同梱されています (要約すると、商用・非商用問わず自由に使用できますが、使用の結果に対して開発元は一切の責任を負いません、といった具合の内容です)。 配布フォルダ内の各構成物の一覧やライセンスについては「 ReadMe_使用方法_必ずお読みください.txt 」をご参照ください。
※ Vnano の実行環境については、別途スクリプトエンジンのソースコードも一般公開しており、 何らかのソフトウェア内に組み込んでご利用いただく事も可能です。詳細はこちらをご参照ください。
この記事中の商標などについて
- OracleとJavaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。この記事は独立著作物であり、Microsoft Corporation と関連のある、もしくはスポンサーを受けるものではありません。
- Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- その他、文中に使用されている商標は、その商標を保持する各社の各国における商標または登録商標です。
|
角度の「度」とラジアンとを相互変換し、図示もするツール |
|
|
|
45度などの「度」の値と、ラジアンの値とを相互に変換できるツールです。対応する角度の図示もできます。 |
|
FizzBuzz の答えを表示するプログラム |
|
|
|
プログラミングの練習問題としても有名な、FizzBuzz 問題の答えを表示するプログラムの例です。 |
|
Vnano版 | 積分値のグラフ描画用データを出力するプログラム |
|
|
|
数値的に積分を行い、結果の関数をグラフに描くためのデータを出力するコードです。 |
|
Vnano版 | 積分値を求めるプログラム (数値積分) |
|
|
|
矩形法/台形法/シンプソン法を用いて、積分の値を数値的に求めるコードです。 |
|
入力された数式を積分して値とグラフを表示するツール |
|
|
|
画面上で数式を入力すると、それを数値的に積分し、値とグラフを表示してくれるGUIツールです。 |
|
シンプソン法による数値積分 |
|
|
|
積分の値を数値的に求めます。台形法よりも高精度な方法として、被積分関数を微小区間内で二次関数近似して求めた面積を足しあげる、シンプソン法を使用します。 |
|
台形法(台形近似)による数値積分 |
|
|
|
積分の値を数値的に求めます。長方形近似よりも高精度な方法として、台形で近似した微小領域を足しあげる方法を使用します。 |
|
矩形法(長方形近似)による数値積分 |
|
|
|
積分の値を数値的に求めます。長方形の短冊(矩形)で近似した微小領域を足しあげる、最も単純な方法を使用します。 |
|
小数(浮動小数点数)から分数へ近似的に変換するツール |
|
|
|
小数(浮動小数点数)を、適当な誤差の範囲内で、近い分数に変換してくれるツールプログラムです。 |
|
円周率1万桁の計算(ガウス=ルジャンドル法) |
|
|
|
ガウス=ルジャンドル法により、円周率を1万桁まで計算するプログラムです。 |
|
試し割り法による素数判定ツール |
|
|
|
試し割り法を用いて、素数判定を行ってくれる簡易ツールです。 |